
緊張して、目に涙をうかべながらも、いつもおりこうさんに治療をする、5歳の女の子〇〇〇チャン。お手紙ありがとう。
先生はとてもうれしかったので、みんなに内容を紹介します。
「いつもむしばをたいじしてくれて、ありがとう。わたしは、先生のことがだいすきです」。
先生の似顔絵もとても上手に書けていて、驚きました。この手紙を読んで、先生のこころは、とても暖かくなり、一日の疲れもとれました。
〇〇〇ちゃんと同じように、むしば治療をこわいと思っているお友達は、たくさん来ますが、これからも先生は、痛くないように治療を頑張ります。
10月24日(日)、プラトンミーティング2010in長野が、
松本歯科大学で開催されました。
講師は、松本歯科大学顎顔面外科学講座準教授 上松隆司先生、東京歯科大学口腔外科学講座 山内智博先生、そこに私を含めた3名が講演を行いました。
当日は、大学病院の先生方、一般開業医の先生方、病院の研修医の先生方にご出席いただき、盛会に行われました。そして、何よりも嬉しかったのが、私が常日頃から尊敬している、恩師の鴨居弘樹先生が大変お忙しい中、応援に駆けつけて下さったこと。鴨居先生、誠に有難うございました。
「実践インプラント臨床 症例供覧を中心にして」との演題で60分間、症例解説をさせていただきました。私以外は、お二人とも現役の大学病院の先生ですので、発表前にはかなりの準備期間とプレッシャーがかかりましたが、無事終えることができ、少しホットしているところです。
しかし、来年2月にパシフィコ横浜で、第30回日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部学術大会が開催され、そこで主演者で発表することになっているため、残念ながら休んでいる暇はありません。今から、来年2月に向けての準備を始めなければ間に合わないのです。
「一度休んだらもう走れなくなってしまうかもしれない・・・。私は、いつまでも、走り続けていたい」。
今年のノーベル化学賞に日本人2名が受賞しました。
根岸英一・米パデュー大学特別教授(75)と鈴木章・北海
道大学名誉教授(80)。
改めて、日本の研究のレベルが、世界においても非常に高い
ことが実証された形になりました。
まだまだ、日本人も捨てたモンじゃないと私は強く感じた。
また、二人とも、受賞対象となった技術について特許を取得
していなかった。つまり、経済的メリットは考えなかったので
ある。根岸氏は「特許を取得しなければ、我々の成果を誰でも
気軽に使えるからと考え、半ば意識的にした」と述べた。
このような立派な研究者達を、日本は今後も育てていかなくては
ならないわけで、そうした意味でも研究・開発の予算を十分に
与えなければ、良い研究は出来ない。資源の無い日本では、この
研究・開発が生命線なのだから。
日本の将来を考えれば、研究・開発に十分な予算をとって挙げて
欲しいものである。
第40回日本口腔インプラント学会学術大会が、
9月17日(金)-19日(日)の日程で、札幌
コンベンションセンターで開催されたので出席して
きました。
17日(金)午前9時30分、松本空港発FDAに搭乗
しました。プロペラ機と違い、FDAはジェット機なので
乗り心地もよく、就航したばかりなので内装もきれいでした。
連休前とあって、観光客の方と学会に参加される先生で、全席
満席の状態でした。約1時間30分のフライトで新千歳空港に
到着し、その後、JRと地下鉄を乗り継ぎ会場に到着しました。
今学会のメインテーマは、「インプラント手術を安全・安心に
行うために」というもので、17日、18日と医院を休診させて
いただきましたが、3日間良い勉強をすることが出来ました。
帰りの便は、新千歳空港から松本空港への便が午前11時30分
と一便しかないので、学会終了まで勉強して、夜、羽田空港に到着
する、JAL便に搭乗し、特急あずさに乗って、帰路に着きました。
今度は、松本歯科大学で10月に開催されるセミナーで口演するため
その準備にとりかかること、来年2月にインプラント学会で発表する
ため事前抄録を書くことなど、忙しい日々に直面していきます。
8月29日(日)、日本口腔インプラント学会関東・甲信越支部
学術シンポジウムが、東京国際フォーラムで行われました。
今回、お手伝いをお願いされていたので、28日(土)診療終了後すぐに東京に向けて出発し、その日の夕方からスタッフの一員としてシンポジウム打ち合わせ会議に参加し、当日、29日(日)は午前7時30分に東京国際フォーラムに出向き、会場の設営、準備を行いました。
インプラント治療は、その技術と材料の発展・進歩により今では、大変有効な治療選択肢のひとつとなっておりますが、天然歯(自分の歯)をいかにして抜かずに残していくのか、また残すためには、その患者さんにとってどのような治療方法が良いのかを考えて、極力、天然歯(自分の歯)の保存努力を優先させる事が、大切であると再認識しました。
当日は、関東・甲信越から多くの会員の先生方の参加があり、大盛況の裡にシンポジウムは終了しました。スタッフの皆さん、お疲れ様でした。

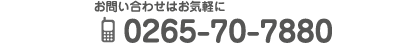
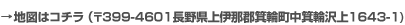
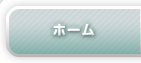

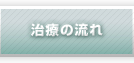
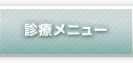

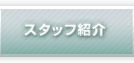

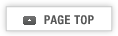



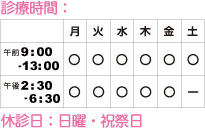
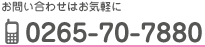

 〒399-4601
〒399-4601