
10月に入りました。朝晩の気温が下がってきましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか?
「認知症について考える」シリーズも今回で、一区切りとなります。益々加速していく超高齢化社会にあって認知症は、「誰にでも起こりうる脳の病気」です。少しでも皆様の参考になってくれればという願いで連載させていただきました。健康寿命「元気で長生き」を目指していきましょう!
(1)発症のリスクを少なくする
認知症は、脳の神経細胞ネットワークが何らかの原因で壊れてしまうことで生じ、加齢が最も大きな原因です。このため、認知症は防ぎようがないと思われがちですが、認知症の約2割を占める脳血管性認知症の予防には、高血圧や高脂血症、肥満などの対策がとても有効です。
また、認知症の半数以上を占めるアルツハイマー病でも、運動をはじめとする生活習慣病対策が発症のリスクを減らす(発症を遅らせる)ことが言われてきています。とくに、楽しく運動することは、脳のアルツハイマー病変を弱めたり、記憶をつかさどる海馬の働きを高めることが示されています。
認知症の発症を完全に防ぐことは困難ですが、生活習慣(運動や食事)に気を配ることで、発症や進行を遅らせることが期待されています。
友達と誘い合ってマッレットゴルフに行く、公園やプールに行って歩く等、とても良いことです。これからでも始めてみてはいかがでしょうか。
(2)脳の活性化を図る
脳の活性化には、いろいろな方法がありますが、大切なことは楽しく行うことです。
仲間と一緒に昔の遊びや仕事などを語る回想法、音読や計算などの学習、音楽や絵画などの趣味活動を通じ、仲間と楽しく過ごすなかで、役割を演じ、前向きに生きる決意が湧いてきます。熱中できる趣味を見つけて、伴侶または友達と一緒になって楽しく取り組んでください。1人孤独に家の中に閉じこもるのではなく、外に出かけましょう!
歯科医としての立場からアドバイスさせていただきますと、自分の歯を極力残し、「美味しく食事をいただく」ことがとても大切なことと言えます。自分の歯を一本でも多く残し、咬むことで脳細胞の神経が活性化されます。ご自宅での毎日のブラッシングと定期的に歯科医院での歯周ポケットのおそうじを行うことで、歯が残せるようになってきています。自分の歯を残すということは、認知症の予防にとって非常に大きなものと考えます。どうか皆さん頑張ってください!
認知症は、誰にでも起こる可能性のある脳の病気です。
慣れた場所でも道に迷ったり、最近の出来事を忘れて、同じことを何度も言ったり、買い物の支払いで手間取ったり、急に怒り出すなど病気のために起こる症状がありますが、一番困ったり、不安や恐怖を感じているのは本人であります。自尊心を傷つけないよう、その方の心に寄り添い、余裕をもって対応することが大切なことです。
偏見をもたず、認知症は自分たちの問題であるいう認識をもち、認知症の人やその家族が、認知症という困難を抱えて困っている人であるということに、思いをはせること、また認知症への正しい理解に基づく対応が必要になってきます。
<具体的な対応の7つのポイント>
(1)認知症と思われる人に気づいたら、本人やほかの人に気づかれないように、一定の距離を保ち、さりげなく様子を見守る。
(2)こちらが困惑や焦りを感じていると、相手にも伝わって動揺させてしまいます。自然な笑顔で応じましょう。
(3)複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、できるだけ1人で声をかけます。
(4)一定の距離で相手の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声がけは禁物。「何かお困りですか」「お手伝いしましょうか」「どうなさいましたか?」「こちらでゆっくりどうぞ」など。
(5)相手に目線を合わせてやさしい口調で。
(6)おだやかに、はっきりした滑舌で。高齢者は耳が聞こえにくい人が多いのでゆっくりとはっきりした滑舌をこころがける。早口、大声、甲高い声でまくしたてないこと。その土地の方言でコミュニケーションをとることも大切です。
(7)相手の言葉に耳を傾けて、ゆっくり対応する。認知症の方は急かされるのが苦手です。同時に複数の問いに答えることも苦手です。相手の反応を伺いながら会話をする。たどたどしい言葉でも、相手の言葉をゆっくり聴き、何をしたいのかを相手の言葉を使って推測.確認していきます。(次回に続く)
8月に入り、毎日暑い日が続いていますが、皆さん元気にお過ごしでしょうか?当院に通院中の方も、庭の草取りをしていて急に気分が悪くなり、幸い御家族の方に発見されて、事なきを得たとのお話を昨日してくださいました。まだまだ暑い日が続きそうです、くれぐれも無理をなさらないようにしてください。私は、2日間に及んだ、全員発表研修会無事に終了しました。数多くの臨床結果、研究報告から、今年も大変有意義な時間を送る事ができました。
前回、日本人の平均寿命そして健康寿命のお話をさせていただきました。
超高齢化社会を迎えて、日本にとって最近、最重要課題の一つに上げられているのが、「認知症」です。
7月30日、箕輪町社会福祉協議会主催の「認知症サポーター養成講座」を受講しましたので、この話題を何回かに分けて、取り上げたいと思います。今回は、認知症の現況と将来の予測について解説させていただきます。
<尊厳をもって最期まで自分らしくありたい>
誰もが望むこの願いをはばみ、深刻な問題になっているのが認知症です(2004年12月、痴呆から認知症へと名称が変更されました)。この認知症は、誰にも起こりうる脳の病気によるもので、85歳以上では4人に1人にその症状があるといわれています。私たちが暮らす箕輪町では65歳以上の約1割の方が認知症となっており、年々増えています。日本全体では、現在約210万人ですが、27年後の平成52年(2040年)には400万人程度まで増加することが予想されています。現在、働き盛りのお父さん、お母さんもこの頃には該当する年齢になる計算です。
認知症の人が記憶障害や認知障害から不安に陥り、その結果まわりの人との関係が損なわれることもしばしばあり、家族が疲れ切って共倒れしてしまうことが今後起こりうる事として、心配されています。
「尊厳ある暮らし」を守るにはどうしたらよいか。次回、考えてみたいと思います。
6月が終わり、7月に入りました。一年のうち、もう半分が過ぎてしまった事になります。本当に月日の経つのは早いものだとつくづく感じている今日この頃ですが、皆さんはお元気にお過ごしでしょうか?
私は、所属する研究会の毎年恒例、「全員発表研修会」が今月開催されるため、発表準備のため5月下旬から毎晩、慌ただしい夜(昼間は診療のため)を送っています。
全国各地から、勉強熱心な優秀な先生方が集まってくる勉強会なので、レベルの高い発表が求められます。「いつまでも刺激を受け続けていきたい」と願う私ですが、それでも正直大変です。また、新たにアメリカ合衆国の、ある大学歯学部の資格取得を目指して勉強している最中でもあります。大学名等、詳細は今後ブログでご報告できるよう、今は頑張るのみです。いつもブログを読んでくださっている皆さんも、それぞれの目標に向かって諦めず、どうか頑張ってください!!
すでにご存じのように日本人の平均寿命は、世界トップクラスで、2010年度では男性79,55歳、女性にいたっては86,3歳です。
しかし、日本人の「健康寿命」は、2010年度では男性で70,42歳、女性は73,62歳で平均寿命との差は10年近くあります。
「健康寿命」という言葉を、最近よく耳にしますが、平均寿命との違いは何でしょうか。解説したいと思います。
健康寿命とは、2000年にWHO(世界保健機構)が提唱した概念で「心身ともに自立し、健康的生活できる期間」と定義されています。
平均寿命と健康寿命との差は、日常生活に制限のある「不健康な期間」を意味します。わかりやすく言うならば、平均寿命から介護年数を引いた数が健康寿命になります。
2010年において、この差は、男性9,13年、女性12,68年でした。今後、医療の進歩に伴い平均寿命が延びるにつれてこの差が拡大することが今、懸念されています。従って、平均寿命を延ばすだけでなく、いかに「健康寿命」を延ばすか関心が高まっています。
「なんでもおいしく食べられる」こうした歯科の役割も、健康寿命を延ばす大切な要素となります。ご自分の歯を守るよう毎食後のブラッシングを欠かさず頑張ってください。元気で長生き!目標にしていきましょう。
「歯周病が進行すると、糖尿病や心筋梗塞などの症状も悪化する」。この事は以前、お話させていただきました。お口の中の病気は、お口の中だけに止まらず、全身的な病気とも大きく関係しています。一昔前には、これらの事は、分からなかったことなので、まさに日進月歩です。
そして、今回最新の報告がされましたのでお知らせします。それは、「がん治療前、治療中、治療後の期間に歯科医師等による専門的なお口の中のケアーを行う事で、治療に伴う合併症、副作用減少.入院期間の短縮ができる」と言うことです。出来るだけ分かりやすく解説してみます
がん治療法の中でも、お口に最も影響を及ぼすのが、抗がん剤治療、頭頸部がんの放射線治療です。抗がん剤や放射線は、がん細胞だけでなく同時にがん細胞のまわりの、正常な細胞も攻撃してしまいます。このため、治療が始まると、副作用で強い口内炎や、味覚障害を起こす場合があります。また、唾液減少と体力低下によりむし歯や歯周病が、一気に進行してしまうと言うことも少なくありません。
お口の中の細菌が肺に入ることで肺炎を発症したり、唾液とともに飲み込んだ細菌が手術した部位に感染する可能性もあります。お口の中のトラブルが原因で、がん治療を一時的にストップすることやトラブルに対する治療のため入院期間の延長の可能性も生じてしまいます。
こうしたトラブルを防ぐため、平成24年度改定のがん対策推進基本計画では、「各種がん治療の副作用.合併症の予防や軽減など、患者の更なる生活の質の向上を目指し、医科歯科連帯による口腔ケアーの推進」がもりこまれました。今回は、少し難しい話になってしまいました。
がん治療前には、かかりつけ歯科医でむし歯や歯周病の治療を受けることが大切と言えます。

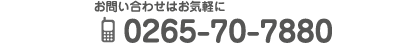
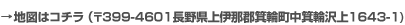
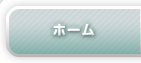

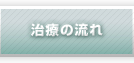
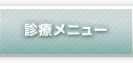

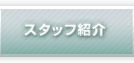

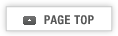



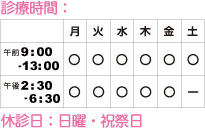
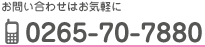

 〒399-4601
〒399-4601