
4月も下旬となりました。例年と比べ、雨の日が多く朝晩と日中の気温差が大きい今日この頃ですが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか?4月から当院にも新卒の歯科衛生士、西藤 智咲(さいとう ちさき)さんが入社いたしました。とても元気よく、明るい思いやりのある新人です。きっと来院中の皆様の緊張をほぐしてくれると期待しております。御迷惑をおかけする事もあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
4月8日(金)~10日(日)の3日間、グアム大学に出張してきました。グアム大学は、私の所属するインディアナ大学(米国:インディアナポリス)と協力関係にあることから、同大において実習が行われました。今まで、インディアナ大学歯学部 客員研究員という立場でしたが、今年から、客員講師 (Visiting lecturer at Indiana University School of Dentistry)) の新たなポジションを仰せつかったことから、インストラクター(指導)という形での出席となりました。インディアナ大学からは、David B.Burr教授、Ronald L.Shew 教授の他、2名の教授がお見えになられました。
私が深く学びたいと考えている、「骨再生治療」の分野においてアメリカではどのような手法を用いて、骨を再生しているのか今後が非常に楽しみですが、まだ実際に臨床応用されるのにはかなり時間がかかりそうです。皆さん予防!どうかしっかりブラッシングを行い、歯の周りの骨が吸収しないよう宜しくお願いいたします。医院のスタッフも頑張って、プラークコントロール等のお手伝いをします。
グアム大学構内の敷地には、南国特有の赤い花が咲き乱れていてとても綺麗でした。ちょうどこの時期、箕輪では桜が満開だったという話を後で聞きました。桜は私の好きな花のひとつなので、お花見できず、とても残念に思っています。
今年に入り、1か月が経過し2月に入りましたが、毎日底冷えのする寒さが続いています。インフルエンザも先月よりは減少傾向にありますが、まだ県の注意報は解除されていません。どうぞ、御自愛ください。最近テレビでも「ヒートショック」と言う言葉を耳にする方も多いのではないでしょうか?そこで、今回このヒートショックについて考えてみたいと思います。
凍えるような冬、寒くてブルブル震えながら浴室に急ぐなんていうことはありませんか?冬の時期、暖房で暖かい居間と暖房のない脱衣所や浴室との差が10度以上になることはまれではありません。この急激な温度変化が短時間のうちに起ると、これに伴って、血圧の急激な上昇や下降が引き起こされます。これを「ヒートショック」と言います。「ヒートショック」は体に大きな負担をかけるため、冬の入浴中に起る突然死の大きな要因となります。例えば、急激に血圧が上昇した場合には脳出血や脳梗塞、心筋梗塞などで死亡する恐れがあります。逆に、急激に血圧が低下した場合は、脳貧血を引き起こし浴槽でめまいを生じてけがをしたり、溺れたりする危険性があります。
<ヒートショックの影響を受けやすい人>
65歳以上である
高血圧・糖尿病・動脈硬化の病気をもっている
睡眠時無呼吸症候群など呼吸器官に問題がある
熱いふろが好き
お酒を飲んでから入浴することがある
<ヒートショックによる事故を未然に防ぐには?>
(1)脱衣所に暖房器具を置くなどして、入浴前に居間と脱衣所との温度差をなくす。
(2)浴槽のふたを開けたり、服を脱ぐ前に、浴室の床や壁にシャワーをまくなどして、浴室を温めておく。
(3)湯船に入る前に、手や足といった末端からかけ湯をして、徐々に体を温めていく。
(4)ぬるめの湯で、入浴時間はほんのり汗ばむ程度にする
(5)入浴の前後には、コップ1杯程度の水分を補給する。
(6)お酒を飲んだら、お風呂には入らない!
私もそうですが、多くの日本人はお風呂が大好きです。特に、一日の終わりにお風呂で体を温めて、湯船でほっこりと一息つく時間を楽しみにしている人も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。でも、お年寄りや高血圧・糖尿病などの病気をもっている人にとって冬の入浴は、常に危険と隣り合わせであることを忘れないようにしたいものです。また、御家族と同居している人は、入浴中に「お湯加減はどう~」、「大丈夫ですか~」などの定期的な声掛けをしてください。
この所、朝晩の冷え込みが大変厳しいですが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか?医院のむし歯を削る器械のコンプレッサーが、屋外の機械室に設置されているのですが、朝凍結していて全く動かないということを、12月に入って2回経験しました。ドライヤーでホースを温めて作動させる。開院して18年になりましたが、初めての経験でしたので、朝から額に脂汗、いや、冷や汗をかきました。それだけ今年は寒さが厳しいと言えます。風邪など引かないよう、どうぞ御自愛ください。
早いもので、2014年が終わりを告げようとしています。皆さんにとって今年はどんな年だったのでしょうか。今私は、一人一人の患者さんに全力を尽くせただろうか?美味しく食べられる喜びを結果として残すことが出来ただろうか?と自問自答しています。
「気力と体力を維持し、集中力を持続させる」このことは、開院してからずっと願い続けていることです。来年も一生懸命に頑張る所存ですので、どうぞ宜しくお願いいたします。
来年の干支は「羊(ひつじ)」羊は、めでたい善良な動物で、同じ行動をとって、大勢で暮らすことから、「群」の漢字は「羊」が語源となって形作られたそうです。群れをなす羊は家族の安泰、いつまでも仲良く平和に暮らす意味を持っています。
2015年が、皆様にとりまして良い一年でありますよう、心からお祈り申し上げます。どうぞ良いお年をお迎えください。
以前から、御夫婦で定期的に歯のメインテナンス(お掃除)に通院していらっしゃるMさん。Mさんは昨年11月、急に具合が悪くなり、救急車で病院へ緊急搬送された。この時は、もうすでに意識はなく、担当医から脳梗塞と診断され、「この2~3日が峠で、最悪の場合があることは覚悟しておいてほしい」と告げられた。「主人の意識がまだ戻らないのです」奥様は泣きながら私に話をしてくださった。
Mさんは、音楽が好きで仲間とバンドを結成して、ボランティアで老人福祉施設や介護施設に出向き演奏しては、入所されている方々を励まし続けてきたことは、Mさんからお話しを聞いて私も知っていたので、とてもこの時ショックを受けました。「なんとかもう一度再起して欲しい」祈るような気持ちになりました。
それから月日は流れ、いくつもの季節が過ぎ、1年が経過した今年の10月のことです。Mさんは後遺症は残るものの、手押し車で来院されました。私は待合室にいらっしやるその姿を見たときに一瞬自分の目を疑いました。でも、間違いなくMさんです。この時、「人間の持つ生命力は凄い」と胸がとても熱くなりました。入院期間中は、バンド仲間が度々訪れては「皆でもう一度演奏しようよ!」と励まし続けてくれた事が生きる力になったと話してくださった。そんなMさんの回復ぶりを見て仲間は「奇跡が起きた」と喜んでくれているということも・・・。
お口の中はどうなっているのだろうか?。診察してすぐに不安は安心へと変わった。以前と同じきれいな状態が保たれていたのである。とてもきれいですねと問いかけると、「内の家内が欠かさず仕上げ磨きをしてくれていたから」と笑顔のMさん。
付き添われてきたMさんの奥様は、「主人がもう一度復活してくれると、ずっと信じていたから・・・」。私はこの時、御夫婦が「強い絆」で結ばれていることに感動しました。
殺伐とした世の中ではあるが、悪い話ばかりではない。Mさん御夫婦と出会えて、私はとても幸せだ。
台風11号が去ってから、このところ毎日お天気が悪く、気温も10度近く下がりました。昨夜は、医院の駐車場ですず虫を発見し、その音色に秋の訪れを感じました。皆さんお元気にお過ごしでしょうか?
厚生労働省は閣議に、2014年版厚生労働白書を報告しました。
白書は、高齢化の進展を踏まえ、介護を受けずに日常生活を送れる期間を示す「健康寿命」と平均寿命との差を縮めていくことが重要だと指摘。
同省が14年2月、成人5000人に行った調査で、自分が幸福かどうかを判断する上で重視することを選択式で回答してもらったところ、「健康」が54,6%で最多。特に65歳以上では71,9%に上った。
日本の健康寿命は2010年時点で、男性が70.42歳、女性が73.62歳と、ともに世界一である。これは、各国における医療制度の中でも、取分け日本は「国民皆保険制度」が充実した先進地であることの証しであると言えます。こうして考えると、日本は諸外国と比較しても、暮らしやすい、素晴らしい国だと実感できます。ただ、平均寿命との差は、男性9.13歳、女性12.68歳となっている。人は誰しもが、周囲の人や家族に迷惑をかけずに、健康で元気な生活を送りたいと強く願っていると思います。このためには、運動や栄養に配慮した食事を現役時代から行い、生活習慣改善を行う必要があります。このことは、どこか歯とよく似ていて、抜けてしまった後、もっと若い時からしっかり磨いておけば良かったと後悔するのとよく似ていると思います。テレビの影響からか最近、患者さんからよく聞かれるのが再生医療についてですが、現在の研究進捗状況からして「再生医療で歯の周りの骨を作る」のはまだ相当時間がかかります。IPS細胞の日本、ES細胞のアメリカ、両国においても骨再生実用化のめどは未だたっていません。
残念ですが私たちにとって今出来ること、それは「予防」。これを継続的に行っていくことです。

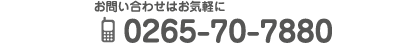
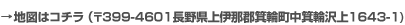
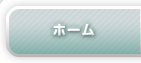

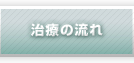
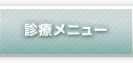

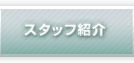

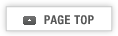



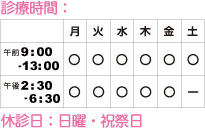
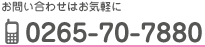

 〒399-4601
〒399-4601