
2016年も早いものであと数日で終わるを告げようとしています。
お陰様で、当院は今年開業20周年を迎えることが出来ました。
一重に、私やスタッフのことを信頼して通院されて下さっている患者さんに心から感謝申し上げます。本当に有難うございます。
この20年間さまざまなことがありましたが、今はまだうしろを振り返る時ではないと考えていますので、これからもしっかり前を向いて 「すべては患者さんのために」を医院の理念と使命と心して、2017年も努力と精進を重ねて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。幸いにも現在は、同じ方向を向いて頑張ってくれるスタッフにも恵まれました。今のスタッフに感謝です。さらにスタッフの増員を図りより質の高いサービスの提供が出来るように頑張ります!!
「 望みを失わなかった者にのみ、道は開ける 」
今年の大河ドラマ、真田丸で真田昌幸が残した言葉です。私はこの言葉がとても好きなので、いつもブログを読んでくださっている皆様にこの言葉を捧げ、2016の挨拶に代えさせていただきます。
2017年が皆様にとりまして、良い年でありますよう、スタッフ一同御祈念申し上げます。
11月に入り、朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。いつも私のブログを「楽しみにしている!」とおっしゃってくださる方々、有難うございます。お元気でしょうか?私は、お陰様で元気にしています。10月下旬は、日々の診療とアジア口腔インプラント学会が韓国、釜山で開催され出席と忙しい毎日を過ごしてきました。
前回まで、糖尿病、誤嚥性肺炎などの全身疾患と歯周病の関係について解説してきました。今回は、心筋梗塞・脳梗塞との関係についてなるべく分かり易く解説していきます。
今まで、心筋梗塞が歯周病と関係していることはほとんど知られていませんでした。「心筋梗塞で運ばれてくる患者は皆、口が臭い」東京医科歯科大学病院に勤めていた循環器内科医の鈴木淳一(東京大特任准教授)は、医療現場で何気なく交わされている会話が気になっていました。そこで、歯科医と共に、心筋梗塞など急性冠動脈症候群の患者を調べたところ、全体の3割で口の中から歯周病菌を検出したほか、この菌が血液中に入り込んでいることを示すデーターも得られ、発症に関わっていることが分かったのです。
歯周病菌は、食べ物のかすと唾液が混ざってできる歯垢(プラーク)や歯石の中で増殖し、傷んだ歯肉の表面から血液に入って全身をめぐり、心臓や脳の動脈の内壁に取り付いて、お口の中のプラークと同じものを形成するため、血管の流れが悪くなることによって、心筋梗塞や脳梗塞が発症しやすい環境となるということです。
私たちが暮らす長野県ではどうか?長寿県であり、がんによる死亡率は全国平均よりも低い反面、心疾患や脳血管疾患など動脈硬化の絡む病気による死亡率は全国平均を上回っています。
40~50歳代の歯周病の割合が多く、三分の一程度の人しか歯科検診を受けていないという報告があります。
歯周病を積極的に治療することで(プラークコントロール)、心筋梗塞や脳梗塞等の循環器の病気のリスクが下がるかどうか突き止める研究が現在行われています。分かったことはまたお知らせしますね。
お盆が過ぎても、連日のように気温が高く残暑が厳しいですが、皆さんは、お元気にお過ごしでしょうか?この時期、リオオリンピックが重なって毎晩夜更かしでテレビ観戦という方、多いのではないでしょうか。
最近、夏バテと寝不足で歯ぐきが腫れて痛い!という方が多く来院さています。しっかり食べて、睡眠時間を確保してこの夏を乗り切っていきましょう!
前回、糖尿病と歯周病の関係について概要を説明させて頂きました。
今回はもう少し踏み込んで、なるべく解りやすく解説していきます。
<糖尿病とお口の中の環境>
(1)お口の中が乾燥する
高血糖状態では、浸透圧の関係で尿がたくさん出ます。その結果、体内のが減少するとともに唾液の分泌量が減り、喉やお口の渇きという症状が現れます。唾液には、食べ物を消化する働きの他に、口の中を浄化したり、傷を治す働きもあり、歯周病を防ぐように作用しています。高血糖のために口の中が乾燥しているときは、その作用が低下していて、歯周病の原因菌が繁殖しやすく、歯周病が進行しやすい環境になってしまいます。
(2)唾液などの糖分濃度が高くなる
お口の中は、唾液で常に潤っています。この唾液は、もともとは血液から作られています。高血糖の状態では、糖分濃度が高くなり、歯周病の原因菌が繁殖しやすくなります。
(3)細菌に対する抵抗力が低下する
高血糖状態では、細菌と戦う白血球の働きが低下することが解っています。感染防御機構が十分に機能しなくなり、このために様々な感染症にかかりやすくなり、感染症である歯周病も当然、怒りやすくなります。
(4)傷を治そうとする力が低下する
プラークが形成された歯周組織では、細菌によって引き起こされる組織の破壊と、それを何とか治そうとする働きのせめぎあいが続いています。高血糖状態では、組織を治そうとする働きが低下し、糖尿病で歯周病の進行が早くなることに影響しています。
<歯周病は生活習慣病、糖尿病も生活習慣病>
歯周病と糖尿病は、生活習慣病です。歯周病を起こしやすくする生活習慣とは、歯磨きがきちんと出来ていないことや、糖分の多いものを好んで食べたり、間食をとり過ぎるなどの食習慣、口呼吸(鼻で息をせず、口で呼吸すること)、歯ぎしり、精神的ストレスがあげられます。このうち、食習慣や精神的ストレスは糖尿病を起こしやすくする生活習慣でもあり、喫煙は糖尿病の合併症を起こしやすくする生活習慣です。
近年では、「糖尿病患者の歯周病を徹底的に治療、予防することで、血糖コントロールが改善された」という報告がよく見られるようになりました。私の息子が通う、新潟大学歯学部はこの分野の最先端の研究が、現在行われています。
糖尿病と歯周病を同時にきちんと治療していけば、必ず双方に良い影響を与え合うことは、間違いありません。
今年は例年と比べて5月の平均気温が高く、長期予報によりますと猛暑になるのではと予想されているようです。患者さんの中には、炎天下のなか屋根の修理をしていて、熱中症になり、はしごから降りる途中で意識を失ないそのままドクターヘリで病院に搬送されて、頭を7針縫う大けがをしたという話をしてくださった方もおりました。命に影響することはなく、本当に不幸中の幸いで良かったとお話をお聞きし、胸をなでおろしました。今年は今から熱中庄対策が必要となっていますので、皆さんも体調管理にくれぐれも努めてください。
今回は、糖尿病と歯周病の関係についてなるべく解りやすく解説していきます。
糖尿病と歯周病がどうして関係するの?と思われる方も多いのではないでしょうか。近年、糖尿病と歯周病の関係が解明されてきたのです。
(1)糖尿病の人はそうでない人と比べて2倍強の頻度で歯周病が起こり やすくなる。
(2)糖尿病の人は歯周病がより重症化しやすい。
(3)血糖コントロールがよくない人は歯周病がより重症化しやすい。
(4)歯周病が重症化している人ほど血糖コントロールがよくない。
(5)歯周病の人は糖尿病になる確率が高くなる。
(6)歯周病の人は現在問題なくても糖尿病予備軍であることが多い
歯周病がある人は、たとえ糖尿病と診断されるほどの高血糖ではな いとしても、HbA1c(過去1~2か月間の血糖値の平均を表す 検査値)が高い人が多いことが示された。
(7)糖尿病の人が歯周病をしっかり治療するとHbA1cが改善する。
慢性感染症である歯周病に対して徹底的な歯のお掃除を行うと、血 糖コントロールが改善する。またそれとは逆に、血糖コントロール が悪いと歯のお掃除だけ進めても、歯周病がなかなか良くならない。
紙面の関係で、(1)~(7)については次回また説明していく予定です。
ようやく私たちが暮らす箕輪町も春めいてきました。
皆さんいかがお過ごしでしょうか?今年は、例年と比べて雪が少なく雪かきは、一回きりと助かった半面、インフルエンザが流行しましたね。まだ、流行っているようですので、うがいと手洗いしっかり行ってください
前回から、歯周病と全身疾患との関係について取り上げました。今回は、高齢者にとって問題となっている誤嚥性肺炎(ごえんせい肺炎)についてなるべく解りやすいように解説していきます。
日本人の死亡原因の第4位は、この肺炎です。肺炎で死亡する人の94パーセントは75歳以上であり、90歳以上では死亡原因の2位と順位が上がるとても怖い病気です。
「誤嚥とは?」
食べ物や飲み物を飲み込む動作を「嚥下(えんげ)」といい、この動作が正しく働かないことを「嚥下障害(えんげしょうがい)」といいます。食べ物や飲み物、胃液などが誤って気管や気管支内にはいることを「誤嚥」といいます。
「誤嚥性肺炎とは?」
誤嚥性肺炎は、細菌(食べかす)が唾液や胃液と共に肺に入り込んで生じる肺炎です。高齢者の肺炎の70パーセント以上が誤嚥に関係していると言われています。再発を繰り返す特徴があり、それにより耐性菌が発生し、抗菌薬治療に抵抗性をもつことがあり、そのため優れた抗菌薬治療が開発されている現在でも治療困難なことが多く、高齢者の死亡原因となっています。
「誤嚥性肺炎の予防は?」
食後、お口の中にたまった食べかすをハブラシ等を使って取り除き、清潔なお口の中の環境づくりに努める(口腔ケアー)。特に、自分では歯を磨くことが出来ない高齢者や脳梗塞の後遺症により手に麻痺が残っている方の場合、家族の方が磨いてあげることが、誤嚥性肺炎を防ぐ有効な手段となります。また、総入れ歯の方では、入れ歯の中に食べかすが多く残っていますので、食後入れ歯をきれいに洗ってあげることも大切となります。

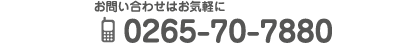
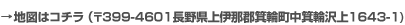
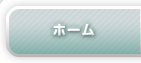

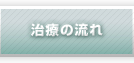
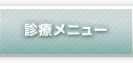

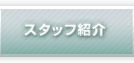

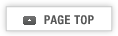



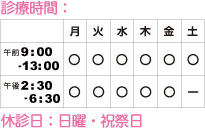
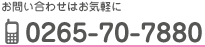

 〒399-4601
〒399-4601