
最近テレビ番組でも、歯周病と全身疾患との関係を取り上げた番組が多く見受けられます。健康志向の高まりから、少し前では敬遠されていた教養番組が今では視聴率が高く、当医院でも多くの患者さんから質問がありますので、今回はこのテーマについて何回かに分けて詳しく説明していきます。(私事で大変恐縮ですが、昨年12月30日父が急逝し、2月14日(日)四十九日の法要を無事済ますことが出来ました。年末から毎日が慌ただしく、ブログの更新がなかなか出来ず、私のブログをいつも楽しみにして頂いている皆さんに、ご迷惑をおかけしすみませんでした)。
<歯周病と全身疾患との関係> 第1回:概要
歯周病は、う蝕(むし歯)と並ぶ歯科の2大疾患のひとつで、歯肉の腫脹(はれ)や痛み、歯を支える骨(歯槽骨)の破壊が起こる慢性の炎症性疾患疾患です。
最終的には歯が抜けてしまうため、食事や会話なでの日常生活に大きな支障をきたします。軽度のものも含めると、驚くことに成人の役70~80パーセントの人が歯周病に罹患していると言われています。
近年、歯周病が糖尿病や誤嚥性肺炎、早産などの原因となることが明らかになり、歯周病が単に口の中だけでなく、全身の健康を脅かす病気であることがわかってきました。
気道や血管を介して肺や心臓に入り込んだ歯周病の細菌が肺炎や心疾患の原因となったり、歯周病によって誘導された炎症性物質が糖尿病や早産を誘発することが、多くの疫学調査や基礎研究から明らかになってきました。
次回は、もう少し詳しくそしてなるべくわかりやすく、それぞれについて説明していきます。
一般工業分野における、CAD/CAM 。(ComputerAidedDesign/Computer Aided Manufacturing)技術の発展・進歩は目覚ましく、ハイテクノロジーとして、航空宇宙分野・自動車分野などにおいて設計および制作技術にさまざまな変化をもたらしてきている。
歯科における、CAD/CAM技術は、他の工業分野と比較してその成長は遅く、旧態依然とした状態が続いてきていた。近年、かぶせものに金属ではなく、高強度、高靱性があるため加工が難しかった、ジルコニアという材料をCAD/CAM技術で製作できるようになり、一部は保険適用(かなり制限はありますが)になった。以前は、適合に不安があったCAD/CAM技術が急速に進歩し、改善されたことが非常に大きい。このことで、材料も含めたかぶせものの治療方法が今後世界で大きく変わろうとしています。
一方、歯科用CAD/CAM技術を応用したデンチャー(入れ歯)については、専用のCADソフトがないこと、加工用ブロックが流通していないことなどから、実用化には至っていません。しかし、これまで避けることがでかなかったレジンの重合府歪みの問題を解決できるだけでなく、ソフトが開発されることで、模型と高さを決めるデーターを入力することで、入れ歯の設計を簡単にコンピューターでできるというパラダイムシフトをもたらそうとしています。
<光学印象の進歩とCTデーターとの照合による入れ歯作成>
今現在、入れ歯を作製する場合、直接患者さんの顎の状態を型取り器を用いて印象をとらなくてはなりません。しかし、この光学印象の分野での研究がもっと進むことにより、直接お口の中で型をとらなくても、顎の形態や高さ、幅の解析が可能となり、これに患者さんのCTデーターを組み合わせることによって、入れ歯が出来る時代が将来実現するかも知れません。お口の中で型をとるのは、想像以上に患者さんにとって負担が大きく、特に高齢者にとっては、呼吸が苦しく快適なものとは言えません。将来、本当にあくまで将来ですが、光学印象の研究と開発が進歩し、これを臨床と組み合わせシステム化し、日本から世界に向けて発信されていくことを願っています。
今年は、気候の変化が激しく大雨による洪水被害が茨城県、栃木県、宮城県で発生しました。尊い命が失われ、また家屋も甚大な被害に見舞われました。自然災害に遇われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。毎日当たり前に生活できる事は、幸せなことなのだと不平や不満を言ってはいけないと、つくづく感じる1週間となりました。
9月13日(日)インディアナ大学歯学部 (IUSD : 米国)定例研修会が、都内において開催されました。午後からの講演会には、講師として<天皇陛下執刀医>として有名な、順天堂大学医学部 心臓血管外科教授 天野 篤先生が登壇されました。2012年2月、天皇陛下の心臓バイパス手術に成功し、NHK「プロフェッシナル仕事の流儀」にも御出演されましたので、多くの方がご存知だと思います。
タイトルは、「高齢化社会の医療におけるQOLの追及」と題して行われました。難しい内容ですので、なるべく解りやすく説明します。今日本は高齢化が進むと同時に、平均寿命も延びています。これは医学の進歩による恩恵ですが、同時に健康寿命が延びるかどうかが、問題視されているのです。平均寿命から健康寿命を引いた差が大きいと、介護期間が長くなり、人として尊厳を保ちながらより良い生活の質の向上(QOL)が図れなくなってしまうと心配されるからです。
天野教授は、心臓バイパス手術等の外科手術は人間の命を救うだけではなく、健康寿命も伸ばせるような手術にしていかないといけないと考え、新たな低侵襲の手術法に取り組んでいるとの事です。私の歯科の領域ですと、歯周病を予防し美味しく食事が食べられる、食べるのが楽しみだというお口の状態にする事が、健康寿命を延ばす事に貢献出来る手段になると考えます。
天野教授は天皇陛下の執刀に成功し、名声を得ました。しかしこの事に満足せず、向上心を持ち続けて、さらに努力されており、この姿に私は深い感銘を受けました。
7月20日(海の日)に梅雨明け宣言がだされてから、8月7日現在まで毎日暑い日が続いていますが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか?ここ数日は、気温が35度を超える猛暑日となっています。今まで経験したことのない暑さですね。避暑地、長野県でも熱中症のため救急搬送される方が、連日新聞で報道され、後を断ちません。昨年までは、朝晩は中央アルプス、南アルプスから吹き降ろす心地よい風のおかげで気温は下がり、窓を開けておけばなんとか過ごせていました。このため、自宅にエアコンが入っていないお家は、今でもとても長野県内は多いように感じます。私が子供の頃にはエアコン無しの夏を過ごしていました。それが今年は、気温だけ都会化してしまいました。こうした環境下では、熱中症に対して十分な注意が必要となります。
熱中症は、軽度のけいれん、中等度の熱疲労、重症の熱射病の3つに分類されます。症状は、頭痛や疲労感を主とすることから、俗に「暑気あたり」といわれる状態や、筋肉がこむら返りを起こす熱けいれん、脱水が主体で頭痛や吐き気をもよおす熱疲労、体温が40度を超え、意識がなくなる最重症の熱射病までさまざまです。
<応急処置>
(1)休息
体を冷却しやすいように衣服をゆるめ、安静にする。
(2)冷却
涼しい場所で休ませる。風通しのよい日陰、エアコンの効いた部屋に移動する。また、氷嚢、氷塊などで、わきの下、首まわり、脚の付け根などを冷やし、体温を早く冷ます。
(3)水分補給
意識がはっきりしていれば、水分補給(スポーツドリンク)を与える。意識障害や吐き気がある場合は、医療機関での点滴が必要で、救急車を呼んで至急病院へ搬送する。
天気予報によると、まだまだ暑い日が続きそうです。熱中症対策を万全にして、今年の夏を乗り切りましょう!
7月19日(日)、20日(海の日)の2日間開催された、毎年恒例スタディーグループの全員発表研修会。第10回となる節目の今回は、約120名が全国各地から参加しました。自身の症例発表とセッションの座長、今年も無事終わり少しだけホットしています。
長野県内も本格的に梅雨入りし、毎日じめじめとしたお天気ですが
皆さんお元気にお過ごしでしょうか?
6月7日(日)、インディアナ大学歯学部(IUSD : 米国)のカンファレンスが都内において開催されました。
インディアナ大学からは、全米歯科大学協会副会長で、歯学部学部長のDr. John Williams, 副学部長の professor MichaelJ,kowlik, professor Vanchit John, professor David Burr を始めとする教授陣が来日されました。
昨年は、Poster Presentaition を行いましたが、今年は、大学から依頼があり、 Oral Presentaition (口頭発表)を行いました。お蔭様で、発表内容については教授陣から高い評価を頂くことができ、客員講師としての重責を果たす事が出来ました。
インディアナ大学歯学部のフェローは、アジア地域だけでも、日本以外に韓国・中国・シンガポール・マレーシア等と各国にいます。教授陣はその各国を視察し、どこの国の発表レベルが高いかを客観的に判断し、大学にとってメリットが得られないと考えれば、もう来年から来日する事はありません。こうした観点から、今回の私を含めた日本人医師9名の発表は、責任重大でした。英文原稿の作成から始まり、単語の発音は、一字一句よりネイティブに近い音がだせるようにと神経をすり減らしました。私の英文原稿に興味のある方は、ホームページ内に掲載してありますのでどうぞお読みください。今は無事発表が終わり、また月曜日から通常の診療を行っていますので、ここの所休みが全く取れなかった影響か、ほんの少しだけ疲れました。
「気力と体力を維持し、集中力を持続させる」これは、いつも私が唱えている言葉。これからも努力し、頑張っていこうと強く思います。いつも私のブログを読んでくださっている皆さんも、「目の前の壁を乗り越え」どうか頑張ってください。

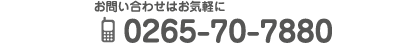
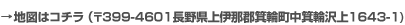
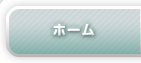

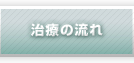
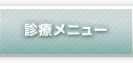

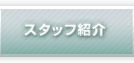

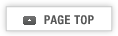



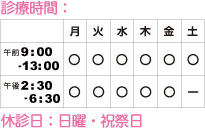
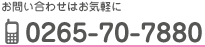

 〒399-4601
〒399-4601